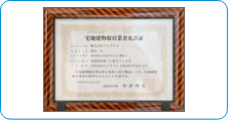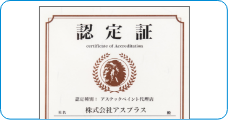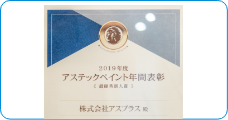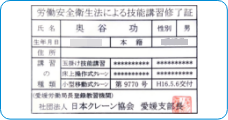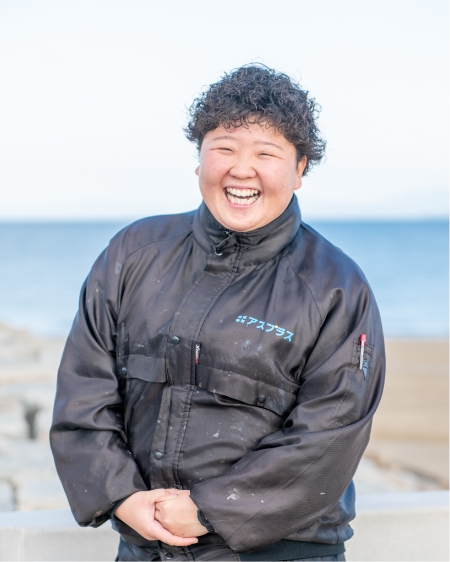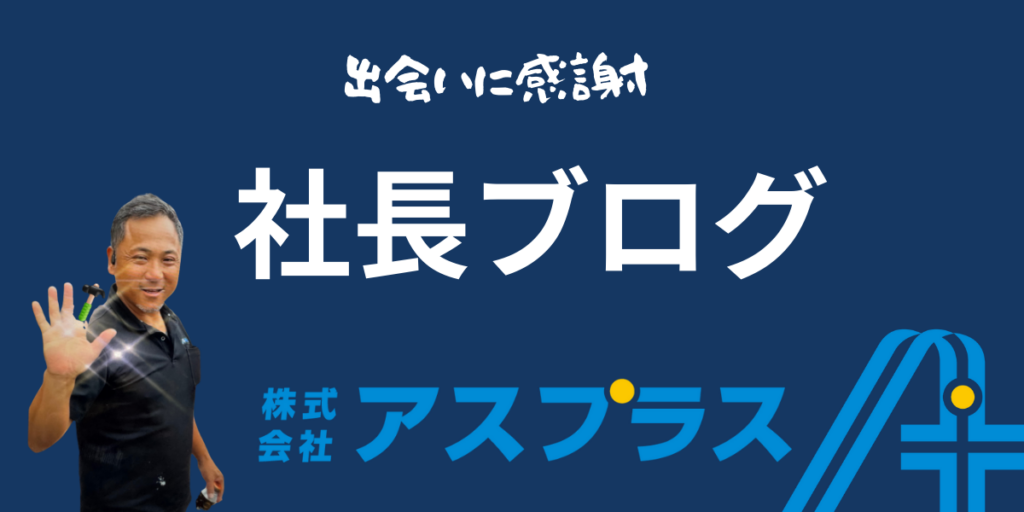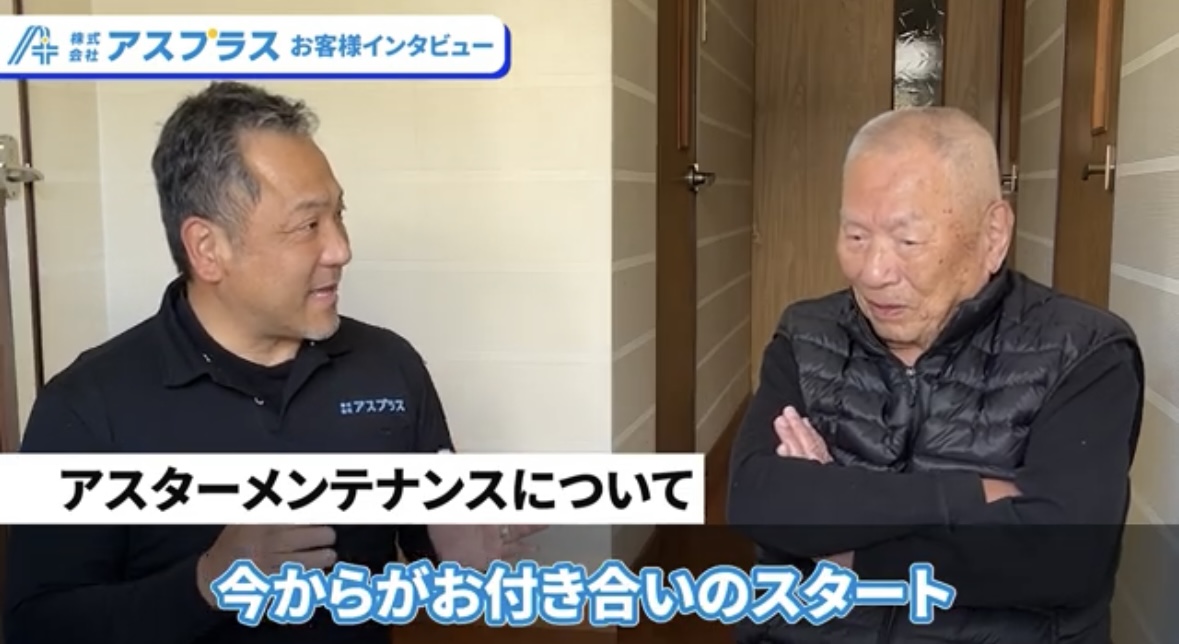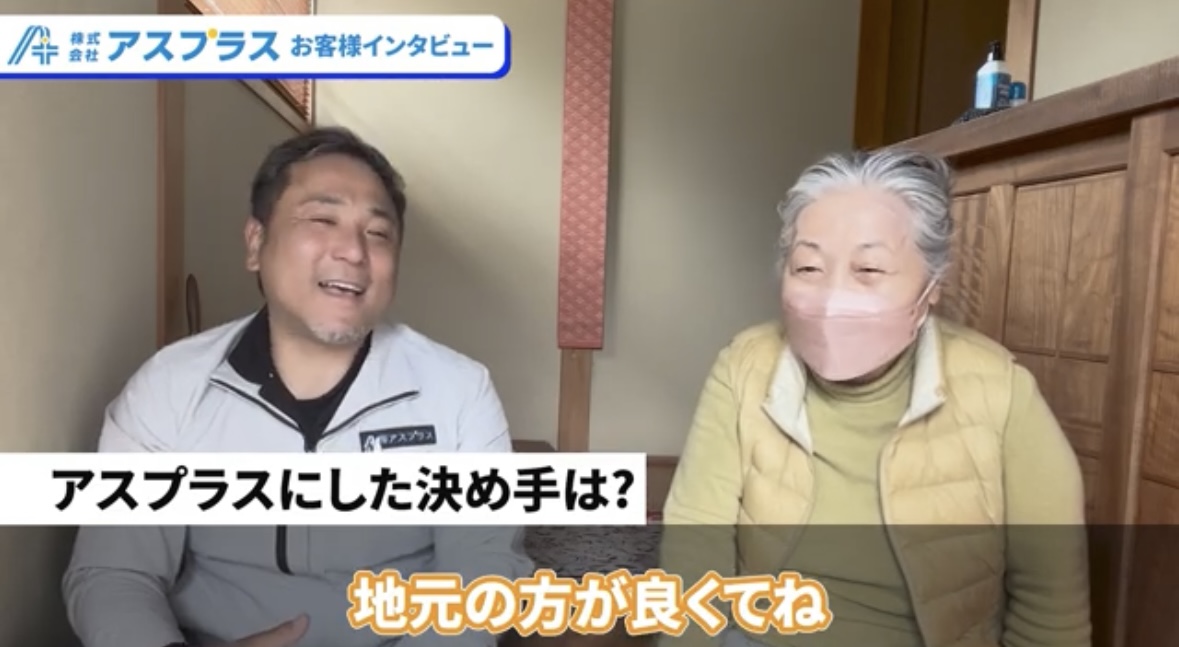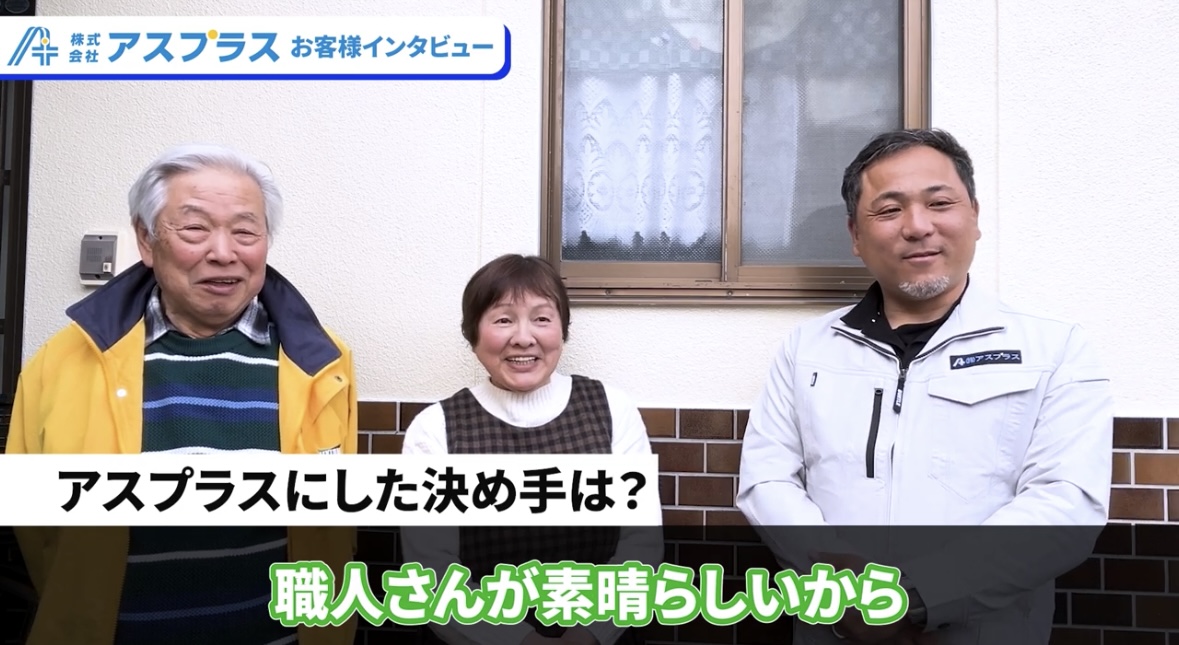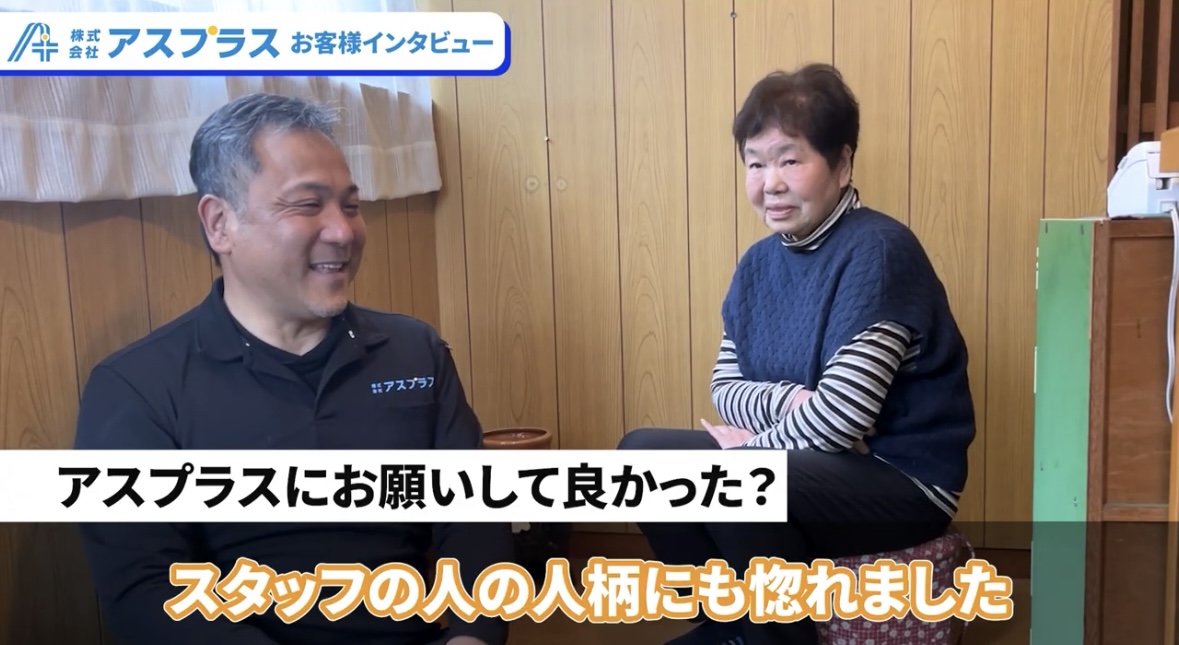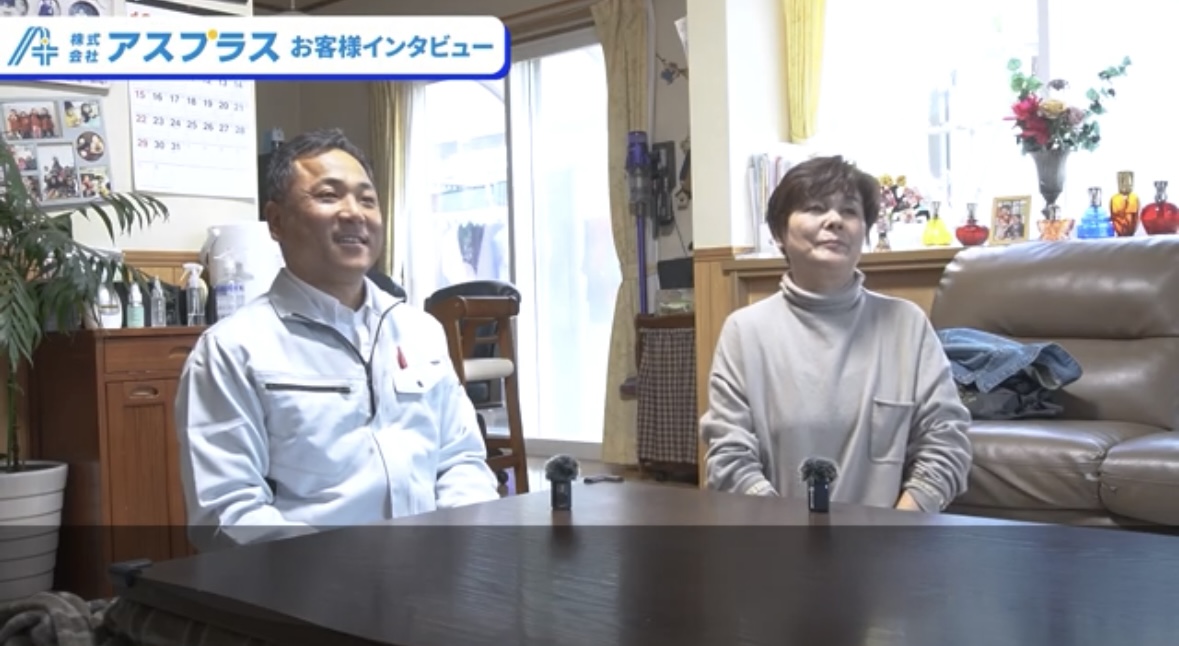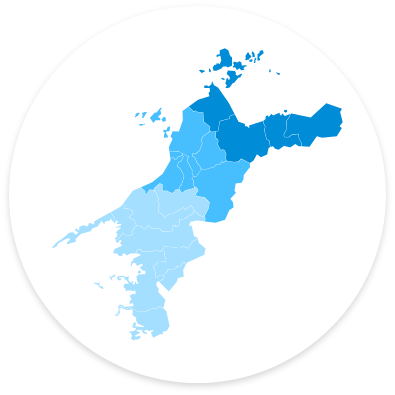松山市大山寺 外壁木部塗装 板金塗装 雨漏り ひび割れ K様邸 ~木部編~

こんにちは、乗松です!
今回は愛媛県松山市大山寺にて外壁の木部塗装・板金塗装を行いました!
木部塗装とは、住宅に使用されている木材を守るために行われる塗装です。木材の劣化を防ぐことができます。
しかし、木部塗装の詳しいやり方についてわからない方はいるのではないでしょうか。
そこで、木部塗装の下地処理や手順について解説しています。木部塗装のおすすめ塗料についても紹介しているので、木部塗装を考えている方は、ぜひ参考にしてください!
木部には調湿機能がある
木部には、コンクリートや金属が素材の建材には無い調湿機能があります。調湿機能とは湿気を吸い取ったり、湿気を放出したりして材木内部の水分を調節する機能のことです。
木材を建材として使用すると、湿度が高いときは室内の湿気を吸収し、少ないときは放出して、室内の湿度を快適な状態に近づけることができます。
木部の塗装の必要性
木部は水分を含むと劣化しやすいという特徴があります。そのため、木材の劣化を防ぐために防水機能のある塗料で塗装をする必要があるのです。
塗装をしない状態だと、木材が水分を吸い込んでカビが生えたり、割れやすくなったりします。木材の内部にまで水が浸透すると、内部の建材まで劣化が進むので注意が必要です。
外装の木部を塗装する場合は、より強度の高い塗装が必要になります。目的に合ったタイプの塗料で、木部を塗装して建材を守りましょう。
木部塗装は難易度が高い
木部塗装は、一般的な外壁や内壁よりも塗装が難しく、塗装を成功させるには一定の経験や技術が必要です。塗装をする前の下処理も、他の素材に比べると手間がかかることが多くあります。
また、下処理が大変だからと適当に行うと、塗膜がきれいにできずに施工不良を起こす可能性が高くなるため注意が必要です。
木部の塗装はDIYでも行うことはできますが、木部の塗装に慣れていない場合は施工不良を起こすこともしばしばです。木部の塗装の経験が少ない場合は、最初から業者に依頼した方が確実でしょう。
木部は塗膜が劣化しやすい
木部は、有機物で伸縮しやすいので、表面の塗膜が引っ張られ塗装が劣化しやすい特徴があります。
気候の変動で塗膜が伸び縮みするので、塗装に使う塗料は伸縮性のあるものの方が長持ちします。外装の場合は特に劣化しやすいので、ウレタンなどの伸縮性の高い塗料を使うと良いでしょう。
また木目の塗装を活かすことができる透明タイプは、劣化が早まります。耐久性の方を重視したい場合は透明ではないタイプの塗料の方がおすすめです。
木部塗装の手順
下地処理
まず塗装の前に、木部に塗装しやすいように下地処理をしていきます。パテや木材用のペーパーでケレンを行い、下地を整えます。
下地をきれいに処理しないと、整えていない場所から塗膜が劣化していくので下処理を念入りに行うことが大切です。
下塗り


下地処理が完了したら、1液ファインウレタン木部用下塗りを塗ります。
仕上げ!中塗り・上塗り


上の画像は中塗りです!↑↑↑
下の画像は上塗りになります!↓↓↓


木部に使用する塗料 ①浸透タイプ
浸透タイプの特徴
浸透タイプの塗料は、木材に浸透していく性質を持つ透明な塗料です。主に、木目や木材の見た目を活かしたい場合に使用されます。
木材の見た目を活かすので高級感が出せますが、耐久性は低くなります。浸透タイプの塗料を使うときは、メンテナンスが頻繁に必要になるのでメンテナンスの頻度には注意が必要です。
浸透タイプのメリット
浸透タイプの主なメリットは、塗料が透明なので木材のそのままの質感を維持できるという点です。また、古い塗膜に重ね塗りできるため作業が簡単というメリットもあります。
特に浸透タイプはメンテナンスの頻度が多くなるので、重ね塗りの作業が簡単なのは助かります。浸透タイプの塗料は、耐久性が必要な外装よりも木目の美しさを活かしたい内装で使われることが多いです。
浸透タイプのデメリット
一方デメリットは、防水性が低いという点です。防水性が劣るため、耐久性は透明タイプではない塗料に比べて劣ります。また、ツヤの調整ができないというデメリットもあげられます。
耐久性が低いので外装での使用には向きません。外装に使われている木部の塗装には、後でご紹介する造膜タイプの塗料の方がおすすめです。
浸透タイプ塗料の種類
| 〈透明タイプの塗料の種類〉 | 〈特徴〉 |
| 木材保護色塗料 | ・ステイン(木材用の着色料)に防腐剤や防カビ剤などを含有 ・外装の木部に使用 ・木材の調湿機能を活かしつつ紫外線や雨から下地を保護する |
| 天然塗料 | ・柿渋といった天然素材を原料とした塗料 ・価格がやや高い傾向がある |
浸透タイプの塗料には、主に木材保護色塗料と、天然塗料の2種類があります。
木材保護色塗料とは、ステインという木材用の着色料に防腐剤や防カビ剤などを含有した塗料です。外装の木部に使用されます。
木材の調湿機能を活かしつつ、紫外線や雨から下地を保護する機能があります。
造膜タイプの塗料
造膜タイプの特徴
造膜タイプの塗料は、木部の表面に塗装の膜を作るタイプの塗料です。浸透タイプの塗料と違って、木部の中には浸透していきません。
木材としての見た目を活かすよりも、耐久性を上げたいときに使われることが多いです。また、木材は伸縮する性質があるので、伸縮性の高いウレタンタイプの塗料が向いています。
造膜タイプのメリット
造膜タイプの塗料は、浸透タイプの塗料に比べて耐久性が高く劣化しにくいという特徴があります。またツヤのタイプも多いので、ツヤの調整が可能です。
カラーも豊富なので、木目を活かす以外のデザイン性は高いでしょう。造膜タイプの塗料は、木目が活かせず高級感があるとは言い難いですが、色とツヤを選んで外装のデザイン性を高めることができます。
造膜タイプのデメリット
造膜タイプのデメリットは、木材の質感が失われるという点です。木材の質感を活かしたい場合は、浸透性の塗料を使用する必要があります。
また、重ね塗りができないので、塗り直す場合は古い塗膜を剥がしてから塗ります。浸透タイプの塗料の重ね塗りよりも手間が必要です。
造膜タイプ塗料の種類
| 〈造膜タイプの塗料の種類〉 | 〈特徴〉 |
| 油性調合ペイント | ペンキといえば本来はこれのこと。ボイル油といった植物油が原料。乾燥時間が長く艶が消えやすいため現在ではほぼ使わない。 |
| 合成樹脂調合ペイント | 油性調合ペイントを改良した塗料。アルキド樹脂(フタル酸樹脂)と油成分を原料としている。こちらも性能が高いとは言えないため現在では一部でしか使われない。 |
| アクリル樹脂塗料 | アクリル樹脂を原料とした塗料。一般的な合成樹脂塗料のなかでは耐久性が低い材料。最近では木部には水性を使うことが多い。 |
| ウレタン樹脂塗料 | ウレタン樹脂を原料とした塗料。木部に使う合成樹脂塗料の中では耐久性が高い材料。木部における最近の主流塗料。 |
| 天然樹脂塗料 | 漆といった天然素材を使った塗料。価格が高い傾向にあるが独自の質感があるものが多い。 |
造膜タイプの塗料には主に、油性調合ペイント、合成樹脂調合ペイント、アクリル樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、天然樹脂塗料があります。
油性調合ペイントとは、いわゆるペンキと呼ばれるタイプの塗料です。ボイル油などの植物油が原料として使われています。乾燥時間が長く艶が消えやすいため、現在ではほぼ使われていません。
アクリル樹脂塗料は、アクリル樹脂を原料とした塗料です。一般的な合成樹脂塗料のなかでは耐久性が低い材料で、最近では木部には水性を使うことが多くなっています。
ウレタン樹脂塗料は、ウレタン樹脂を原料とした塗料です。木部に使う合成樹脂塗料の中では耐久性が高い材料で、木部における最近の主流塗料となっています。
次回はこちらのお客様の板金塗装についての記事を更新致します🌟
木部とは材料が木材でできた部分のことで、木部にも塗装が必要です。木部の塗装をせずに放置しておくと、湿気や雨水などを吸収してカビや劣化が早く進行してしまいます。
また、木部の塗装は難易度が高い作業です。DIYで行うことも可能ですが、経験や技術力が必要になります。木部の塗装経験が豊富ではない場合は、業者に依頼して塗装してもらった方が耐久性の高い塗装になるでしょう。
木部の塗装には様々な塗料があり、メリットやデメリットが異なります。塗料ごとのメリット・デメリットを考慮したうえで、目的に合った塗料を使用すると満足度が高くなります。
満足度の高く耐久性の高い仕上がりの塗装にするには、木部塗装の経験が多い信頼できる塗装業者に依頼するのがおすすめです。
木部塗装や、何かお困りの方は是非アスプラスにお任せください☺️
点検、お見積りはもちろん無料です!
お気軽にご連絡、ご相談くださいね^^