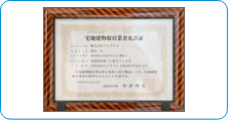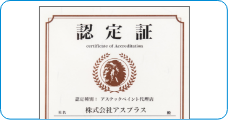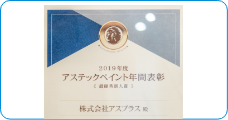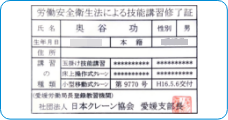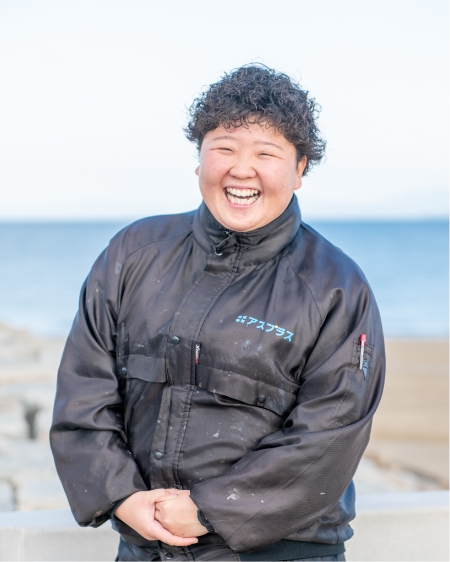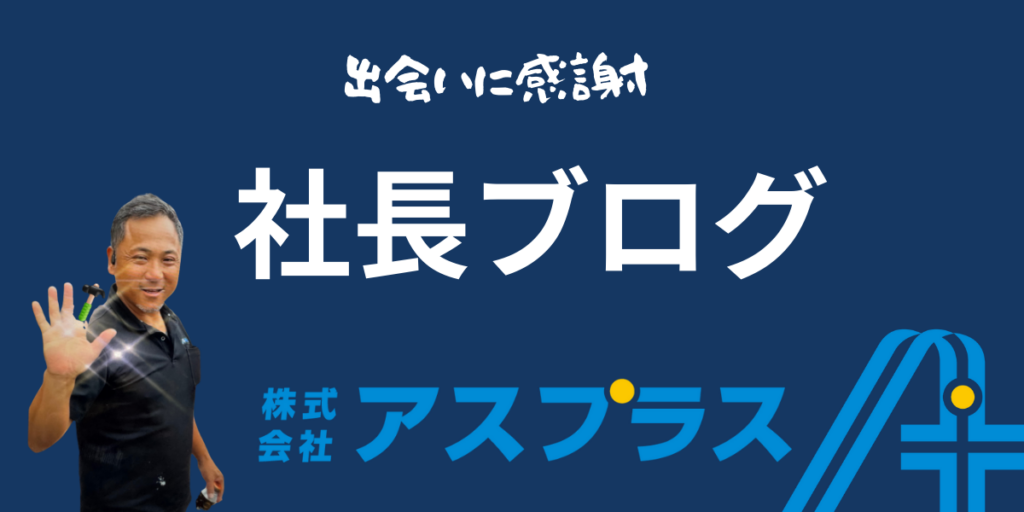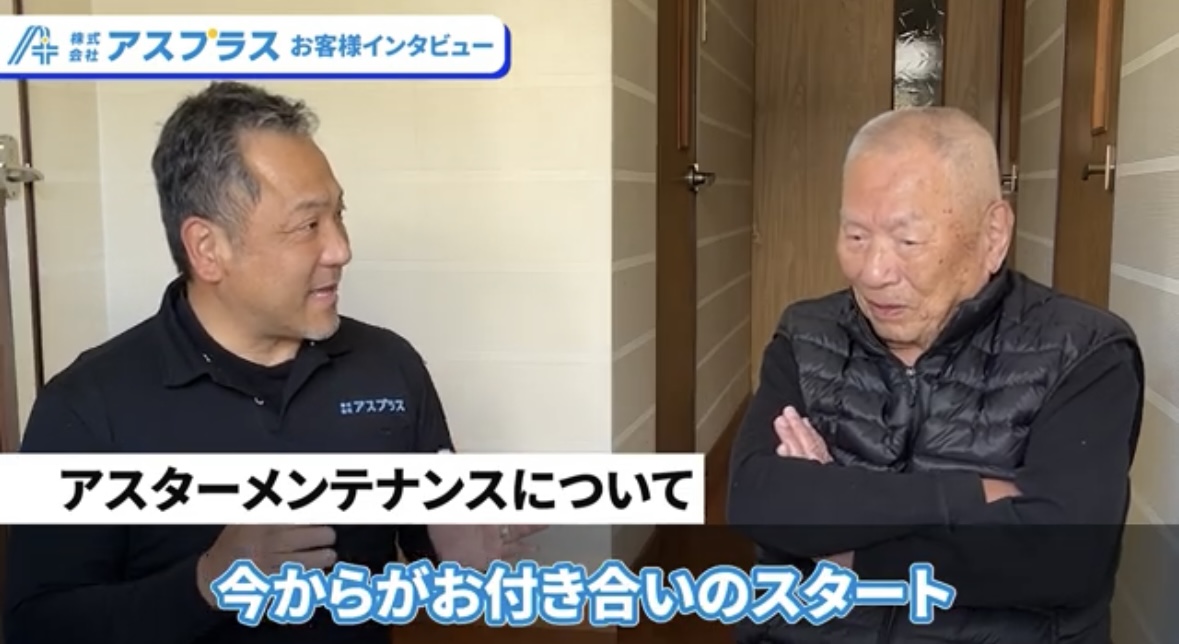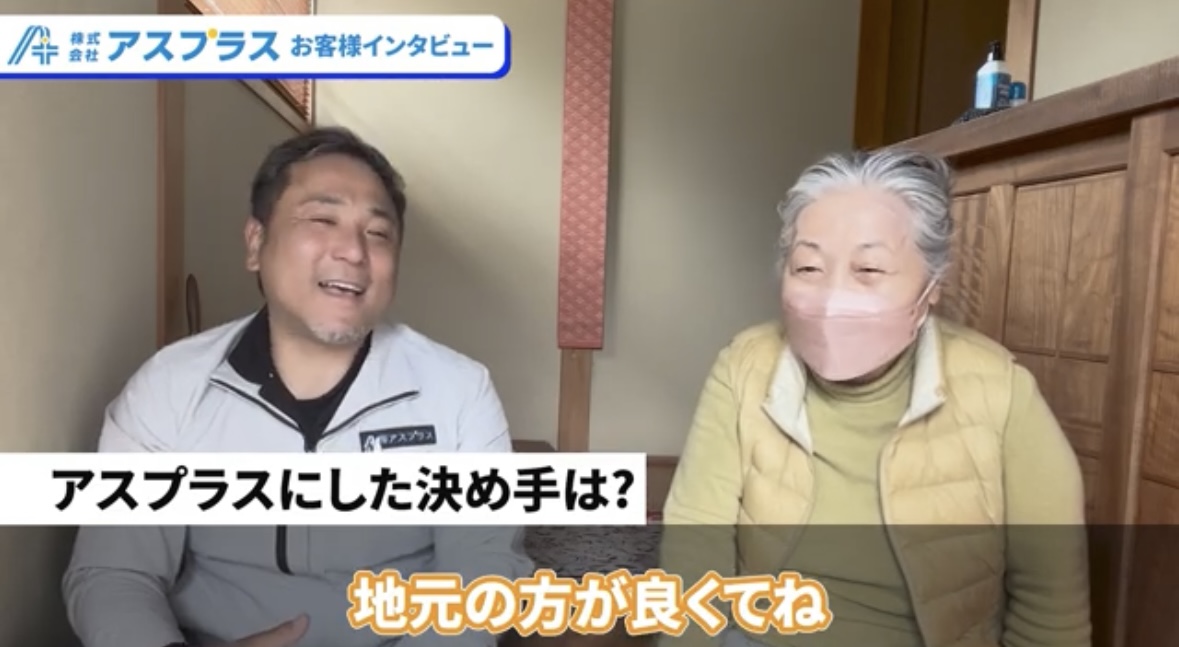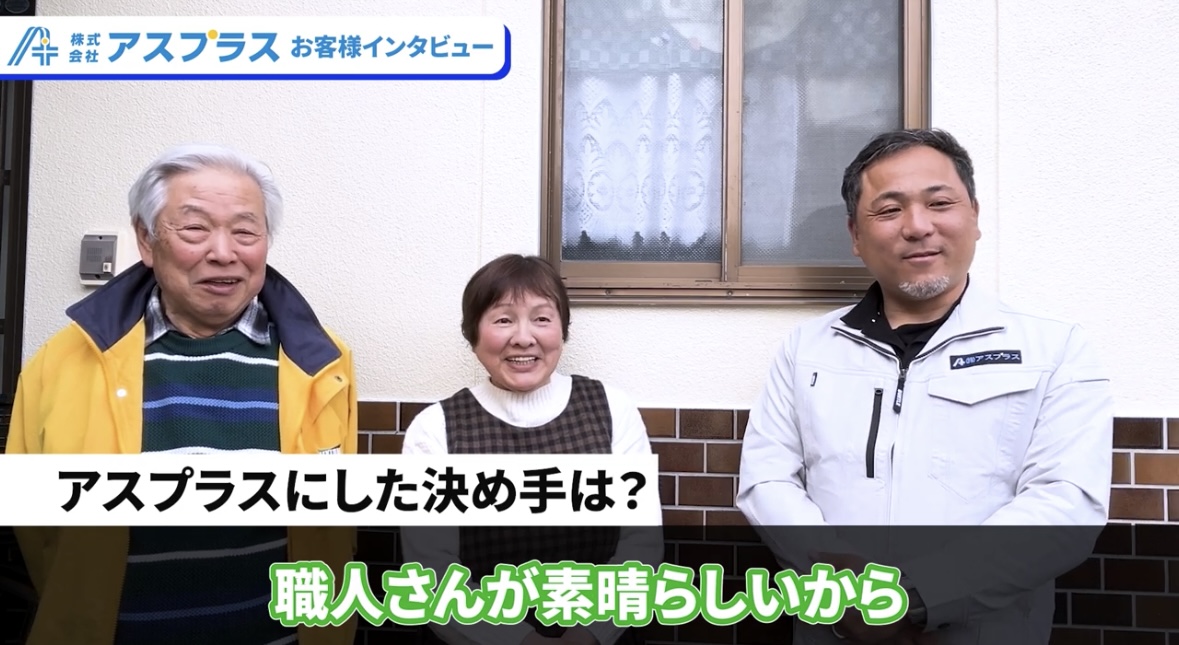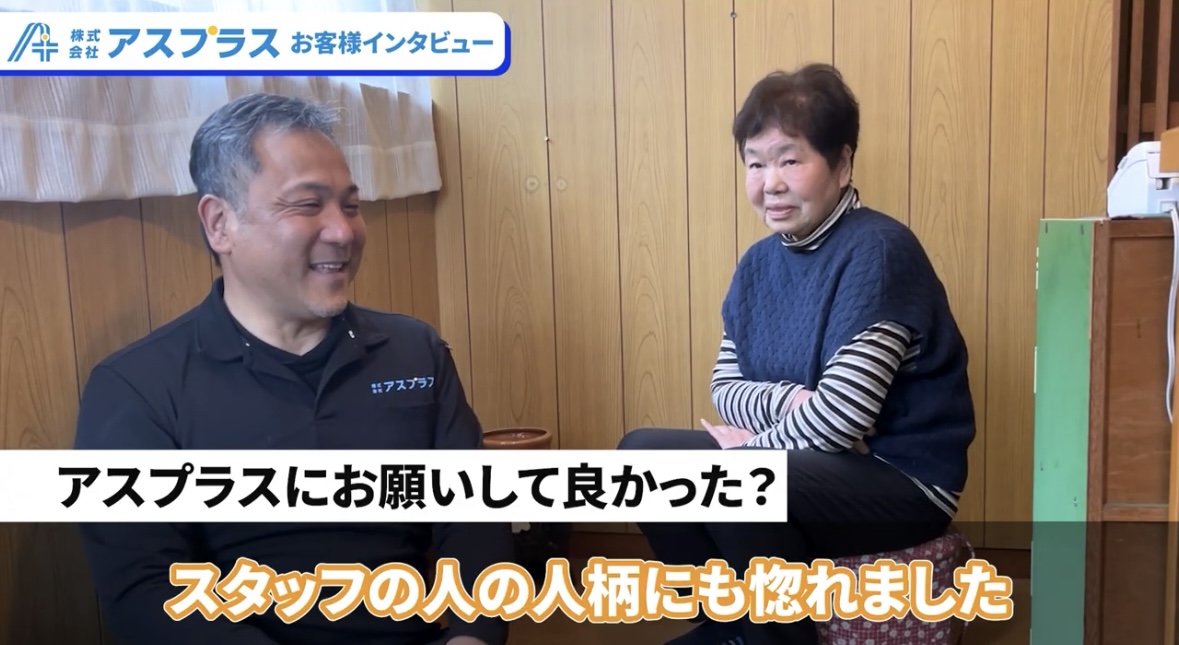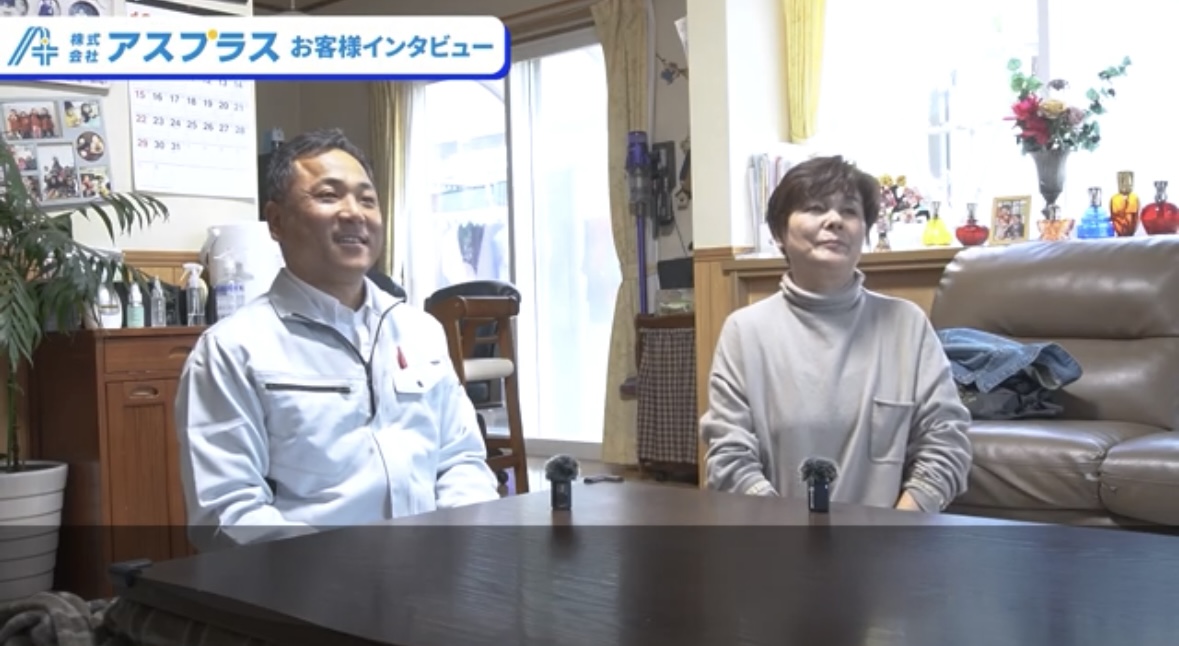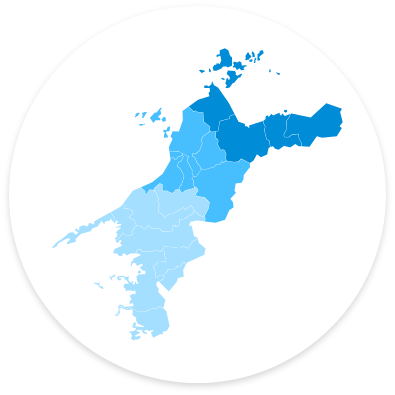外壁塗装で行う木部塗装とは? 雨漏り 割れ 屋根 瓦

こんにちは、乗松です。
今回は、【外壁塗装で行う木部塗装】についてご説明していきます!
木材は軽く加工しやすい性質があり、見た目にも温かみを感じる優れた建材です。和風住宅では外壁の板張りや破風板、庇や縁側などに木材が使用されています。洋風住宅でも外壁の一部にアクセントとして採用したり、ウッドデッキやベランダの手すりに木材が使用されているケースもあるでしょう。
しかし、木材は定期的な塗装を怠り放置すると腐食してしまいます。塗装による保護効果が失われると、雨が降るたびに常に湿った状態になり、ほんの数年で腐ってしまい交換に高額な費用が発生することもあります。
住宅の外部に使用される木材

木材を使用している外装部材と、劣化した際に見られる症状について解説します。
この機会に、ご自宅の外装のどの部分に木材が使用されているかチェックすることをおすすめします。
木材が使用される外装部位
日本の伝統的家屋はほとんどの部位に木材が使用されており、外部にも木材が使用されていることが多くあります。近年は洋風住宅でも外装のアクセントとして使用されています。下記に木材を使用していることが多い部位を挙げてみます。
【和風住宅】
・破風板(はふいた)
・軒天井
・垂木(たるき)
・羽目板(はめいた)
・面格子
・濡れ縁
【洋風住宅】
・破風板(はふいた)
・木製サイディング
・ウッドデッキ
・ベランダ手すり
・木製フェンス
外部に使用される木材の種類
外部に使用される木材の種類には次のようなものがあります。一般的に針葉樹材は軽く吸水しやすい性質がありますので、雨ざらしの環境では腐食しやすいことに注意が必要です。
【針葉樹】
・スギ(杉)
・レッドシダー(米杉)
・ヒノキ(檜)
・ヒバ(檜葉)
・サワラ(椹)
【広葉樹】
・ラワン
・イペ
・セランガンバツ
外部木材の劣化事象

外部の木材が劣化すると、次のような症状が現れます。これらの原因は主に雨水によって木材が濡れた状態が長期間続くと発生しやすいため、定期的な木部塗装によって撥水効果を維持することが外部の木材を長持ちさせるポイントです。
腐食や風化
木材は湿った状態が続くと、腐朽菌が発生して腐食してしまいます。表面上は分からなくても、内部で腐食が徐々に進行して強度が保てなくなり、最悪の場合は崩れ落ちてしまいます。
また、直射日光と風雨に繰り返しさらされた木材は徐々に本来の色が失われてグレー色に変色し、表面が風化して劣化が進行します。
シロアリによる食害
常に濡れた状態にある木材は、シロアリの餌食になりやすくなってしまいます。シロアリは一箇所に発生すると、近くの木材に次々と移動して被害を広げていきます。外部のウッドデッキやフェンスのメンテナンスをせずに放置しているとシロアリが発生して、そのうちに住宅の構造材である土台や柱にまで食害が広がり重大な被害を及ぼす可能性があります。
カビや藻の発生
湿った木材の表面には、カビや藻類が発生しやすくなります。これらは木材を養分として成長し、木部の美観を大きく損ねます。濡れてもすぐに乾燥する環境ではカビや藻類は発生しにくいので、外部に木材を使用するときは適度に日当たりがあり風通しの良い環境で使用することをおすすめします。
木部塗装の効果と塗り替えのタイミング
木部塗装の効果
①木部の美観を保つ
木材の表面に塗装を施すことで、直射日光や雨風の影響による風化を予防することができます。含浸系の塗料であれば木材の風合いをつぶしませんので、木目を活かしつつ長年に渡って木材の美観を保つことができるでしょう。
また、長年の使用により色がくすんだり汚れてしまった木材も、木部塗装によって着色することによって美観を回復することができます。
②カビや腐朽菌から守る
外部用の塗料の多くには防腐剤や防カビ剤が添加されています。菌類などの繁殖を防ぎ木材の劣化を遅らせることで、外部に使用する木材を長持ちさせる効果が期待できます。
③シロアリ被害から守る
防虫成分を含有している木部塗料には、シロアリが忌避する成分が含まれています。成分が有効に働いている限りはシロアリが付きにくく、木材をシロアリの食害から守ってくれるでしょう。
④木材の強度を高める
木材は有機物であり、セメントが主成分の窯業系サイディングや金属と比べて柔らかいため、表面に傷が付きやすい性質があります。木部塗装に含まれる樹脂成分には木材の表面を硬化させる働きがあり、それによって砂ぼこりなどの飛散物で木材表面が傷付くことを防ぎます。
木部塗装のタイミング
一般的な屋根や外壁の塗り替えサイクルは10〜20年ですが、木部塗装はそこまでは持ちません。1年〜5年程度での塗り替えを推奨します。これは、木材は有機物であるため温度や湿度などの気候条件によって収縮と膨張を繰り返すことが要因です。
この伸び縮みがあるために、木部塗装が剥離し効果が失われるスピードも早くなってしまいます。また、含浸性塗料の多くは油性であるため、揮発によって効果が失われていくことも関係します。
劣化が進行してしまうと、塗装によって強度や美観を回復することが難しくなってしまい、新品の部材への交換となる可能性が高くなります。比較的安価な塗装メンテナンスで済むように、劣化の事象が見られたら早めに専門業者に相談するようにしましょう。
木部塗装の塗り重ね
木部塗装の効果を十分に発揮し、均一に発色させるためには数回に分けて重ね塗装をすることが一般的です。外壁塗装と同様に少なくとも2回、塗装面のコンディションによっては3〜4回塗り重ねると長持ちします。
まとめ
今回は外部に使用される木部の部位と劣化事象、木部塗装の必要性について解説してきました。木材は独特の風合いと温かみがあり、住宅の外観に良いアクセントを与えてくれます。しかし風雨にさらされた環境では劣化し腐食しやすいため、マメな塗装メンテナンスが必須といえます。
木部塗装を行う際にも部位や樹種、劣化の進行度合いによってさまざまな塗料の選択肢がありますので、塗装専門業者に相談して最適なお手入れ方法のアドバイスをしてもらうことをおすすめします!
お客様のお悩みや疑問に、豊富な経験をもとに丁寧に対応させていただきます!
お客様の大切な住宅の美観を保ちつつ長持ちさせるための最適な提案をいたしますので、お困りでしたら
お気軽にアスプラスにご連絡、ご相談くださいね🌟